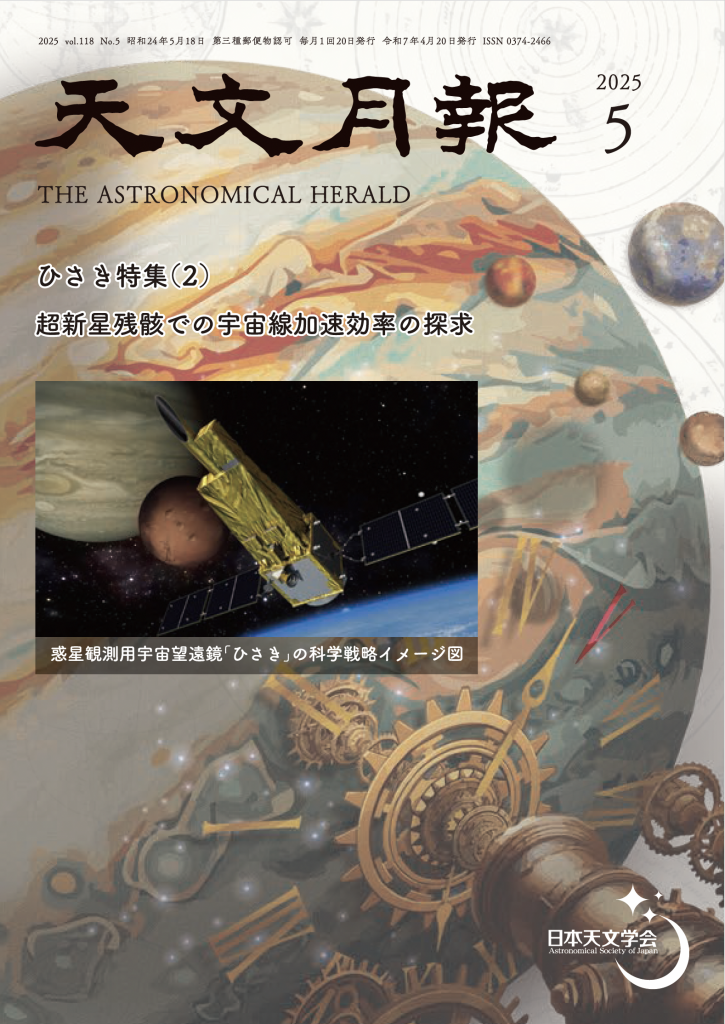高エネルギー天体グループの霜田治朗特任助教が、日本天文学会が発行する「天文月報」5月号に「超新星残骸での宇宙線加速効率の探求」と題する論文が掲載されました。自身の研究成果をわかりやすく一般読者向けに書いたコラム EUREKAの一つに取り上げられ、1912年に発見されて以来、謎とされている宇宙線(特に宇宙線陽子)の起源天体候補とされている超新星残骸の衝撃波で、宇宙線加速効率を天体観測により突き止めるために行ってきた理論研究について解説しています。
100TeVを超えるガンマ線、偏光Hαの観測など、これまでの観測や理論研究を振り返りながら、超新星残骸における宇宙線加速効率までは実証しきれていない現在の状況や、XRISM衛星による革新的な超精密分光観測がもたらす可能性などにも触れ、自身による研究の道すじを振り返る読み物です。霜田特任助教が最後に記した「理論のない観測研究だけでは、『天体Aではこうだったけど、Bでは? 過去・未来では何が起こった・起きる?』という疑問が常に発生し、根本的な『なぜ?』という疑問に答えを出し得ないし、理論研究には観測による検証が必須なのである。Hαと合わせて、次はとにかく観測を更新するというのが、この研究の最前線であると思う」という言葉に、理論と観測が両輪となり進歩してきた宇宙線物理の歴史と、冷静にその先を見据える霜田特任助教の心意気が読み取れます。
日本天文学会の公式Webページ に全文が公表されていますので、ぜひご覧ください。
【論文情報】
霜田治朗「超新星残骸での宇宙線加速効率の探求」,
天文月報 2025.5, pp286-294, https://www.asj.or.jp/jp/activities/geppou/2025/entry1028.html
【日付】 2025-4-20