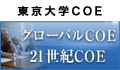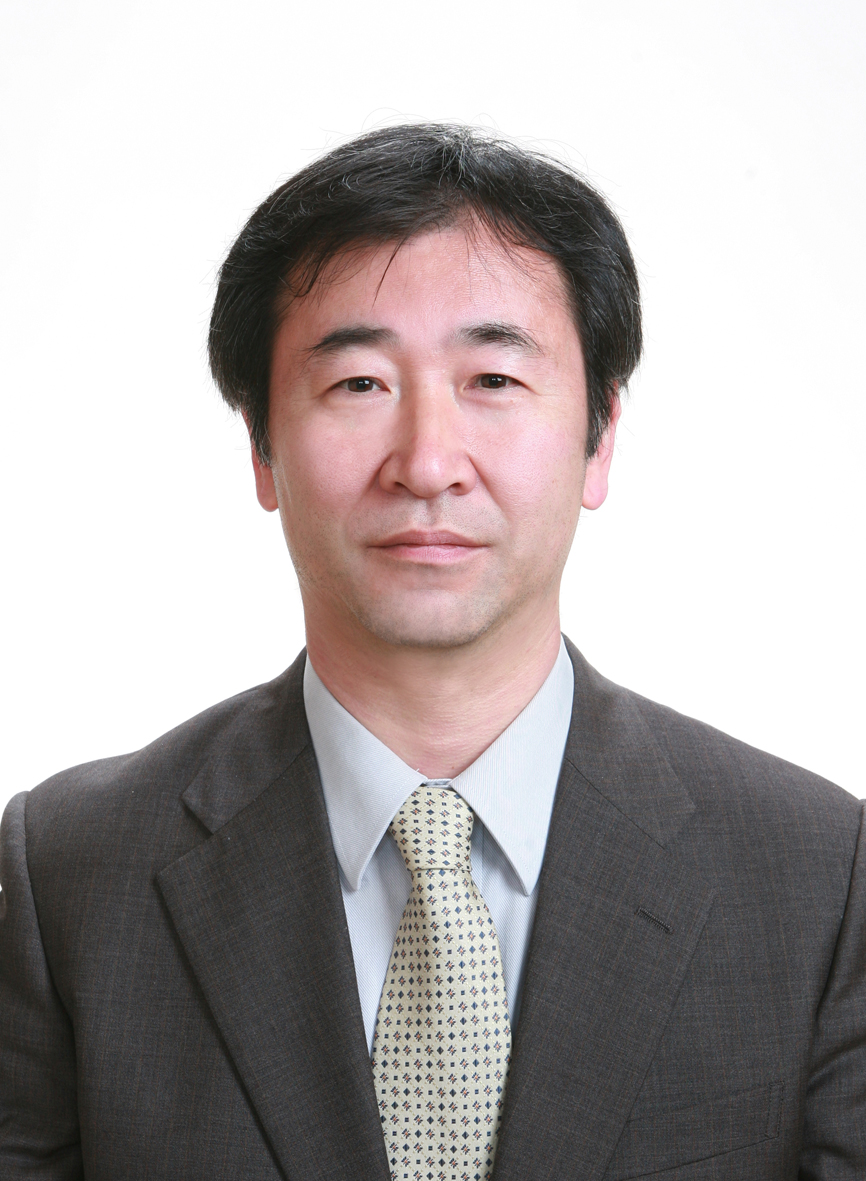
東京大学宇宙線研究所長
梶田隆章
2014年4月1日
平成26年度当初にあたり、ご挨拶申し上げます。
宇宙線研究所は宇宙から飛来する宇宙線の観測と研究を様々な角度から行っています。研究所の歴史は1950 年に朝日新聞学術奨励金で乗鞍岳に建てられた宇宙線観測用の「朝日の小屋」に始まります。その後1953 年に東京大学宇宙線観測所(通称、乗鞍観測所)となりました。この観測所は、わが国初の全国共同利用の施設でした。そして1976年に現在の名称の東京大学宇宙線研究所となり、全国共同利用の研究所として宇宙線の研究を進めてきました。
研究所は宇宙粒子線を研究手段として、動的な高エネルギー宇宙を解明するとともに素粒子物理のフロンティアを開拓する研究を行っています。そのため研究所には、宇宙ニュートリノ、高エネルギー宇宙線、宇宙基礎物理学の各研究部門があり、研究スタッフはどれかの研究部門に所属して研究を行っています。研究所は東大の柏キャンパス内にありますが、それと共に研究所は国内に3つ(岐阜県飛騨市の神岡地下、乗鞍岳(2,770メートル)、山梨県の明野高原)と海外に2つ(チベット・ヤンパーチンの高原(4,300メートル)、アメリカ・ユタの砂漠)の観測拠点を持っています。超新星ニュートリノやニュートリノ振動(質量)を発見した神岡は特に有名なのでご存じの方も多いかと思います。このように研究所では観測しようとする宇宙線の観測に最も適した場所を世界中から探し、そこで研究を行っています。
宇宙線研究所は現在、平成22年から始まった国の共同利用・共同研究拠点制度のもとで、全国及び海外の宇宙線研究者と共に共同利用研究を進めています。毎年100件以上の共同利用研究が全国の宇宙線関連研究分野の研究者の方々によっておこなわれています。したがって、宇宙線研究所の研究成果は全国の宇宙線研究者との共同研究の成果であると言えます。また、宇宙線研究所の研究のほとんどは国際共同研究です。
近年の宇宙線研究分野の発展はめざましく、世界中の研究機関から本当にエキサイティングなニュースが飛び込んで来ます。宇宙線研究所は今後も世界の宇宙線研究の中核をなす機関として世界の宇宙線や関連する研究に貢献していくつもりです。宇宙線研究所では節目ごとに外部の有識者を多く含む将来計画検討委員会を組織して、研究所の将来の中核となる研究を検討してきました。なかでも重力波の観測研究は、研究所として1990年代半ばからの悲願であり、科学的にも極めて重要なテーマとの認識を持ってきました。このようななか、平成22年度文部科学省の「最先端研究基盤事業」による補助対象事業の1つに大型低温重力波望遠鏡(KAGRA)プロジェクトが選定され、また文部科学省の概算要求によって重力波装置を設置する地下空洞の整備が進められています。これらは皆様からの強いご支援によるものです。皆様のご支援に感謝いたします。これを受けて、研究所ではKAGRAプロジェクトをホスト研究機関として、また共同推進機関である高エネルギー加速器研究機構及び自然科学研究機構国立天文台と協力しながら強力に推進するため、重力波推進室を設置し、国内外の共同研究者とともにKAGRAの建設を行い、世界に先駆けて重力波の観測と重力波天文学の創成を目指していきます。KAGRAのための地下空洞は平成26年3月末に完成し、いよいよ現地での建設が本格化します。今後も一層のご支援をお願いいたします。
重力波プロジェクトが建設段階になったことを受けて、研究所ではその先の将来のことを検討すべき段階になりました。そのため将来計画検討委員会を設置して、1年以上かけて研究所の基幹の将来計画をどうすべきかの検討がなされました。その結果超高エネルギーガンマ線天文台プロジェクトCTAをはじめ複数のプロジェクトが高い評価を得ました。また外部評価委員会を平成24年度に設置して、研究所のこれまで6年間の研究活動などを主に評価してもらいました。これらの委員会の報告書は宇宙線研究所のホームページに掲載されていますので、是非ご覧ください。これらの委員会からの報告を受けて、宇宙線研究所では新たな展開を図っていきます。
宇宙線研究所の研究計画を進めていくためには、今後も宇宙線関連分野の研究者の皆さんの支持、大学からの支持・支援が必要なことはいうまでもありません。また国からの支援もますます重要になっていきます。今後とも、宇宙線研究所の研究活動にご支援をお願いしますとともに、本研究所からの研究成果にご注目下さい。