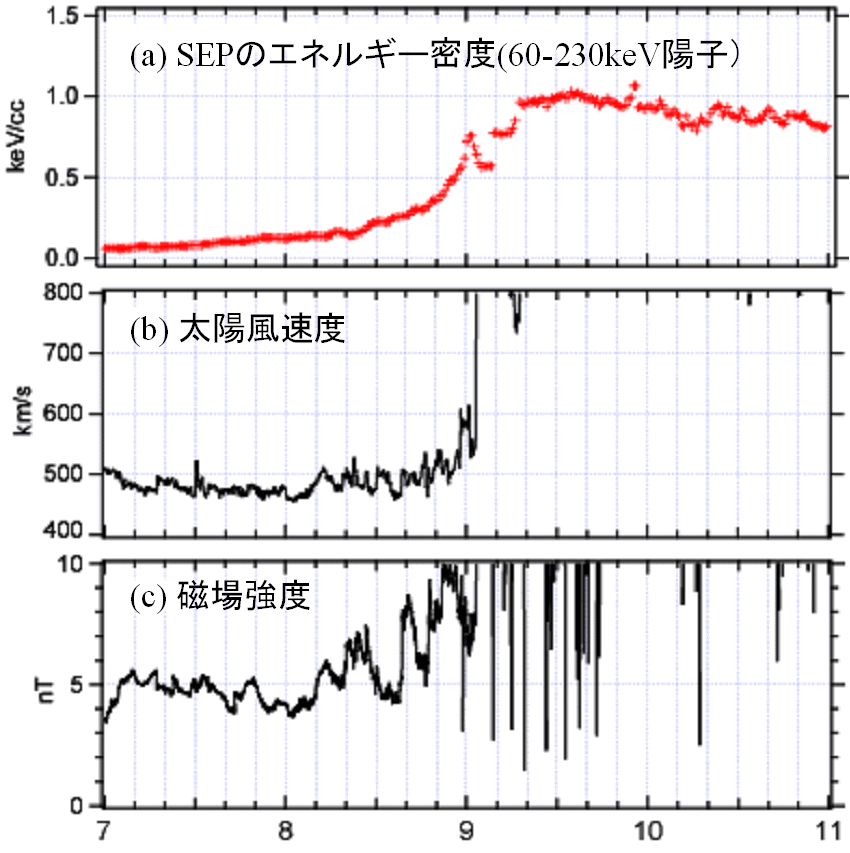
図6: 1994年2月21日7時〜11時(世界時)に観測された(a)SEPエネルギー密度、(b)太陽風速度、(c)磁場強度の変化。図1に示したものと同じ世界時09:03:21の衝撃波到着の±2時間のデータを示す。衝撃波到着前の変化を強調して図を描いたため、衝撃波到着後は(b)、(c)のグラフはスケールアウトしている。衝撃波静止系での速度は上流→下流で減少するが(図5(b'))、(b)では、衝撃波は観測者に向かって運動しているので、速度変化は増大のセンスとなっている。
宇宙線変成衝撃波CRMSの基礎的物理過程の観測的研究は、太陽圏内の衝撃波のうち、いくつかの強いものにおいて実現されてい[9]。ただし、太陽圏で「宇宙線」粒子の役割を果たすのは、それぞれの場合に応じて加速されている非熱的粒子である。例えば、図6の例[10]では惑星間空間衝撃波により加速された数十keV〜数百keVのイオン(Solar Energetic Particles=SEP)がその役割を果たしている。図6で、(a)SEPのエネルギー密度は衝撃波到着(09:03:21)に向け、緩やかに増大している。これは図5(a')にあたるものである。SEPのエネルギー密度の増大分は衝撃波上流の太陽風の運動エネルギー密度の15%に達しており、衝撃波の構造を変えることが期待される。実際、図6(b)に示した太陽風速度の変化を見ると、衝撃波到着以前の20分間に100km s-1の増大が見られる。この変化はこの惑星間空間衝撃波がCRMS性を持つとして期待されるものである。CRMS理論から期待されるように、磁場強度も衝撃波面に向かって増大している(図6(c))。ただし、増大しているのは静的磁場成分B1ではなく、SEP粒子がビームサイクロトロン不安定性を通じて励起したアルフェン波の振幅ΔBであり、衝撃波面の直前(09:00頃)でΔB/B1〜 1程度までの増大が見られている。この例では衝撃波のアルフェンマッハ数は5.8であったが、最近、Bell[11]はマッハ数が数十〜数百の天体衝撃波では磁場増幅ΔB/B1>>1が起りうると提案して議論を呼んだ。定量的な議論は未完成だが、この機構の存在を認める理論家が多く、Bell機構と呼ばれている。
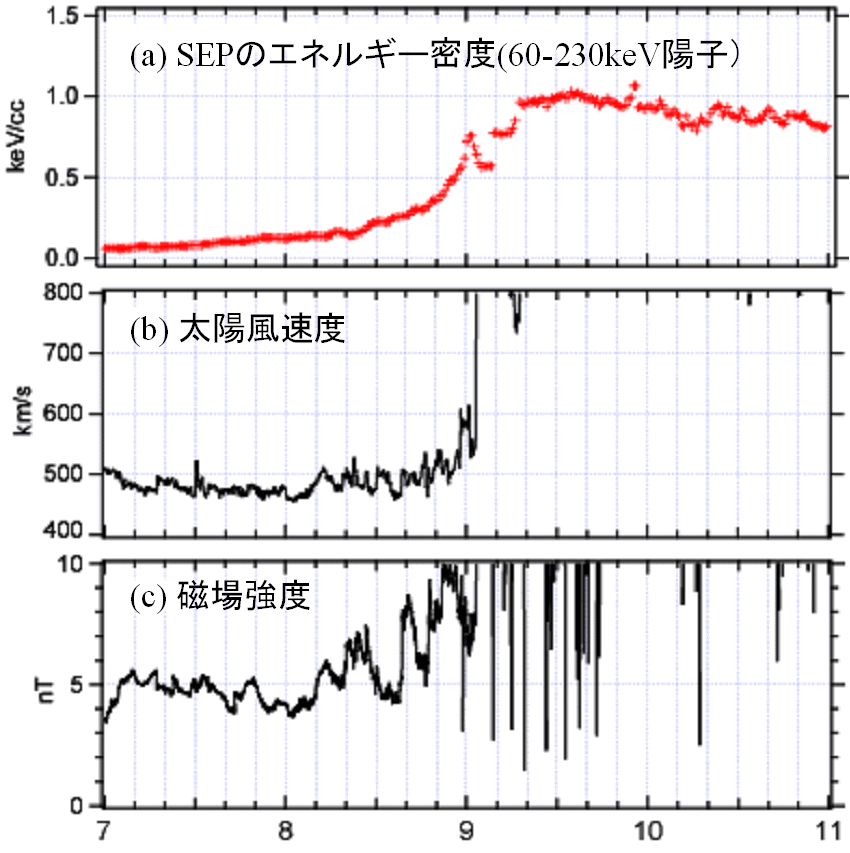 |
← 図6: 1994年2月21日7時〜11時(世界時)に観測された(a)SEPエネルギー密度、(b)太陽風速度、(c)磁場強度の変化。図1に示したものと同じ世界時09:03:21の衝撃波到着の±2時間のデータを示す。衝撃波到着前の変化を強調して図を描いたため、衝撃波到着後は(b)、(c)のグラフはスケールアウトしている。衝撃波静止系での速度は上流→下流で減少するが(図5(b'))、(b)では、衝撃波は観測者に向かって運動しているので、速度変化は増大のセンスとなっている。 |
惑星間空間と違って直接探査のできない遠くの天体における加速領域での磁場強度の推定には、シンクロトロン輻射スペクトル(強度、最大周波数)の観測が使われるが、それらは磁場強度ばかりではなく、輻射にかかわる電子のエネルギーの関数でもあって、なかなか一意的な決定は難しい。それでも、超新星残骸内の磁場が恒星間空間の平均磁場強度である3μGの数十倍以上であるとする推定が沢山[12]あり、Bell機構の存在を示唆するものと考えられている。この稿の最初に、銀河宇宙線の起源は超新星衝撃波による加速が有力と述べたが、実は、超新星衝撃波の時間発展を考慮して標準理論を厳密に適用すると、到達エネルギーは1014eVどまりで、1-2桁足りないことが指摘されていた[13]。到達エネルギーは加速領域の磁場強度に比例するので、Bell機構はこの「エネルギー危機」を解消する「救世主」として待ち望まれていた感がある。