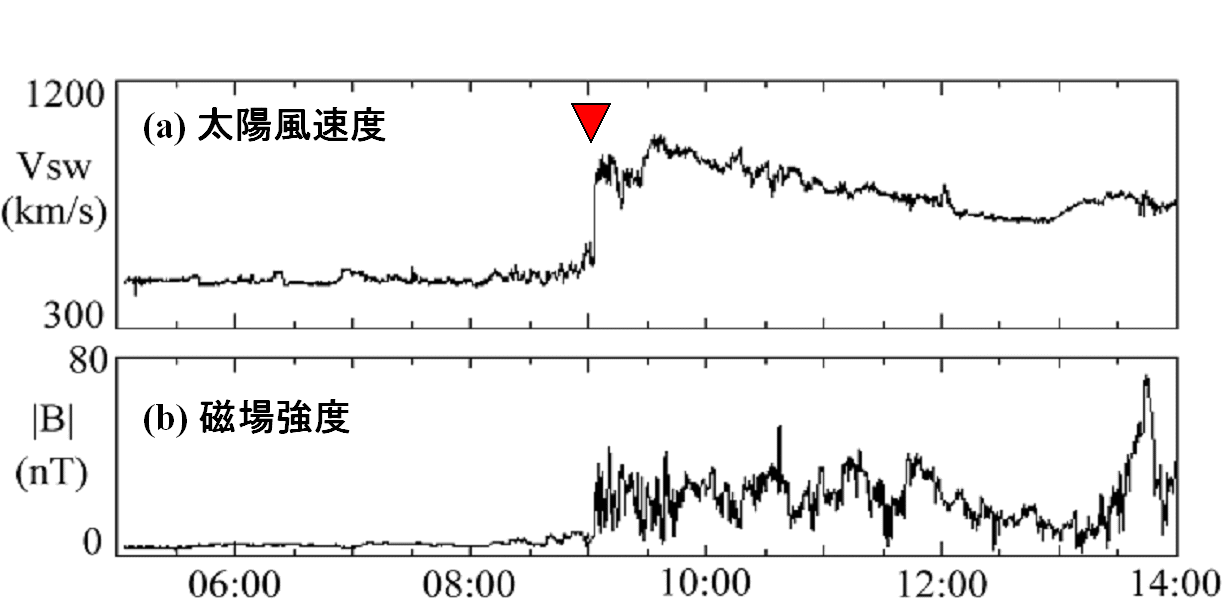
図3: 1994年2月21日5時〜14時(世界時)に観測された(a)太陽風速度と、(b)磁場強度の変化。世界時09:03:21の衝撃波到着を▽印で示す。
(1)に述べたように、宇宙の様々な局面で衝撃波が重要な役割を果たしている。まず、そうした天体衝撃波と、超音速飛行するロケットなどの前面に形成される日常的な衝撃波との違いについて述べたい。衝撃波の静止系では、衝撃波面に流れ込むガス(上流側のガス)は超音速であるが、衝撃波面から流れ出るガス(下流側のガス)は亜音速である。超音速→亜音速の差の分の運動エネルギーは衝撃波面で熱エネルギーへ転化されるが、その転化を担うのが衝撃波面における散逸機構である。大気中の衝撃波と、天体衝撃波の基本的な違いはこの散逸機構の担い手である。大気中の衝撃波では、頻繁な分子間衝突が散逸を担い、衝撃波面の厚みは衝突の平均自由行程の数倍程度である。一方、宇宙のガスは一般に電離しており、中性ガス中の分子間衝突に対応するものは荷電粒子間のクーロン衝突だが、それで現実の天体衝撃波の散逸が説明できるだろうか?図3に、太陽面爆発に伴って形成された惑星間空間衝撃波の地球近傍での観測例を示す[7]。衝撃波到着(▽印)の前後で太陽風速度が約450km/sから約900km/sに増大し、同時に磁場強度も数nTから数十nTへと増大している。これらの速度・磁場の増大は1秒以内に起きており、観測者に対する衝撃波の伝搬速度を考慮すると対応する衝撃波面の厚みは数百km以下であることがわかる。しかし、クーロン衝突に基づいて図3の場合の平均自由行程を計算すると1天文単位を越え、観測された衝撃波面の厚みより5桁以上も大きくなってしまう。すなわち、この衝撃波の散逸機構はクーロン衝突では全く説明できず、別の物理機構が必要であることが明らかである。
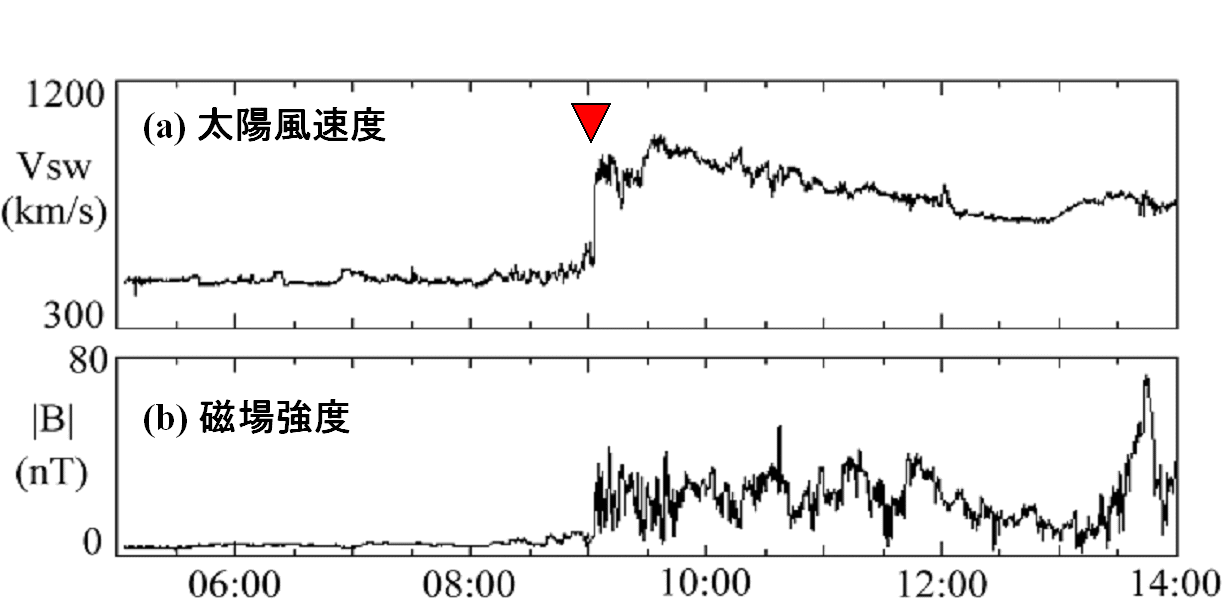 |
← 図3: 1994年2月21日5時〜14時(世界時)に観測された(a)太陽風速度と、(b)磁場強度の変化。世界時09:03:21の衝撃波到着を▽印で示す。 |